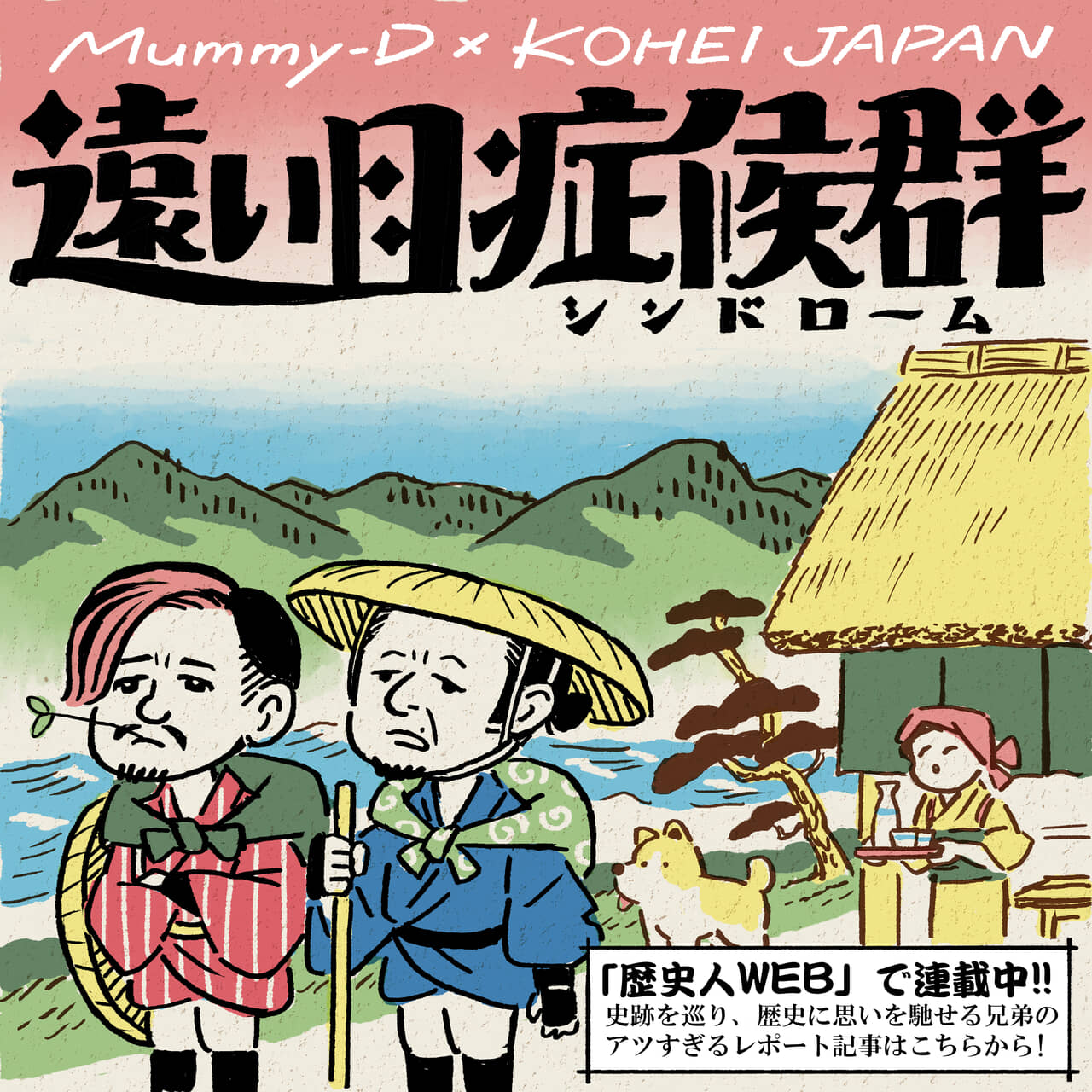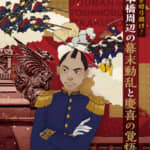変わりゆく江戸・東京の情景を訪ねて~明治維新以降の日本橋に残る江戸情緒
Mummy-D&KOHEI JAPANの遠い目症候群#05
■新紙幣の顔のひとり! 近代日本資本主義の父・渋沢栄一
(by KOHEI JAPAN)
そんなわけで我々は渋沢栄一像にピットイン。いやあかなり大きい銅像だ。ロングコートを羽織り、杖を持って、遠い目をしている。いや、遠い目ではない。なんでも日本最古の銀行である第一国立銀行があった築地の方向を見ているそうだ。なぜか?この「日本最初の銀行」を作った人だからだ。

撮影:Mummy-D
渋沢栄一、他にも肩書きが多すぎて説明が大変なのだが、「近代日本資本主義の父」とだけ言っておこう。数年前にはNHKの大河ドラマ『晴天を衝け』の主人公になったり、今年度7月からなんと新一万円札の顔になるくらいの偉人である。
そんな偉人、栄ちゃんの銅像が何故ここ日本橋、常盤橋門に鎮座しているのか?それは彼の生涯を紐解いていけば垣間見えてくる。
時は幕末。攘夷の志に燃え江戸に出てきた渋沢は、ひょんなことから対抗する幕府側の一橋慶喜(一橋家)に仕えることになる。やがて慶喜が十五代将軍となると、今度は幕臣になるのだ。幕臣渋沢栄一としては、江戸城を守る常盤橋門はとても大切な場所であったに違いない。
さらに言えば、関東大震災で被害を受けた、この日本橋エリアの復旧と整備に尽力したのも栄ちゃん。そして1933年、渋沢栄一財団からの多額の寄付により、この常盤橋公園が整備され開園、銅像も同時に建立されたとのこと。がしかし、第二次大戦の金属供与により撤去、改めて戦後再建されたみたいだ。
そしてやはりこの地区は、金融関係にゆかりのある場所だという事か。常盤橋のすぐ向こう側に日本銀行本店。江戸時代には金座(金貨の鋳造所)が置かれた場所である。日本銀行の開業にも当然栄ちゃんが大きく関わっているしね。
生涯で約500もの企業や団体の設立と育成に関わったといわれている渋沢栄一の銅像、常盤橋門とセットで是非行って、遠い目をしていただきたい。
雨脚が強くなってきたし疲れてきたね。サミイしね。そんなわけで一行は常盤橋から信号を渡り、日銀横の貨幣博物館にピットイン。近っ!渋沢栄一の新一万円札をいち早く拝みに行くじょー。
カネ。それはいつの世も、人間のあらゆる欲望が渦巻く…。そんなカネたちが古代のものから現在のものまできれいに保存、陳列されている。偽造されないために様々なK.U.F.U.を重ね、なおかつ定期的に新札に変えていくという。江戸時代には一日千両のカネが動いたと言われる日本橋。キャッシュレス化が進む今日、カネ(現金)はどう変わっていくのだろう。遠い目。。。
なんてそんなことは微塵も考えておらず、この時点で俺の頭の中は『ああ、もう疲れたなー。そろそろビールのみてえなー。もう終わりでいいんじゃねえの?』など、貨幣博物館だけに「現金」なことを考えているのであった。

貨幣博物館で想像以上に盛り上がる遠い目症候群一行。